| 7.今後の対策 |
|
2000年以降、宇治川では腹口類メタセルカリアの寄生したオイカワやコウライモロコは、2001年冬にも観察されましたが、1尾あたりのメタセルカリアの寄生数が1/10〜1/100程度になっていました。このため、2000年1〜3月のような異常遊泳、大量衰弱事例は起きてなかったと考えられます。その原因として、2000年当時とその後で宇治川における河川流量、渇水等、河川状況に変化があったためではないかと推察されました。 そこで、宇治川天瀬ダム下流域の河川流量に着目して、1999年10月〜2000年2月と2000年10月〜2001年2月の天瀬ダムにおける旬別平均放流流量を比較したところ、1999年10月下旬〜2月下旬の流量が2000年10月下旬〜2001年2月下旬の流量の半分しかなかった(図3)ことが判りました。また、1999年秋〜2000年冬は降雨量、降雪量が少なく、琵琶湖は渇水状態でした。このような気象の影響で河川流量が少なく、流れが緩やかになったため、カワヒバリガイから泳出した大量のセルカリアが下流に流されず、オイカワやコウライモロコに寄生できたと想像されます。河川流量が通常であれば、セルカリアが下流に流され、この水域での大量寄生には至らなかったのでしょう。
したがって、腹口類吸虫が定着した宇治川ではオイカワ等での被害発生の有無は、河川流量の多少に左右されると考えられました。また、セルカリアを泳出させるカワヒバリガイにおける寄生率の高低やカワヒバリガイの生息数の影響を受けるものと考えられました。
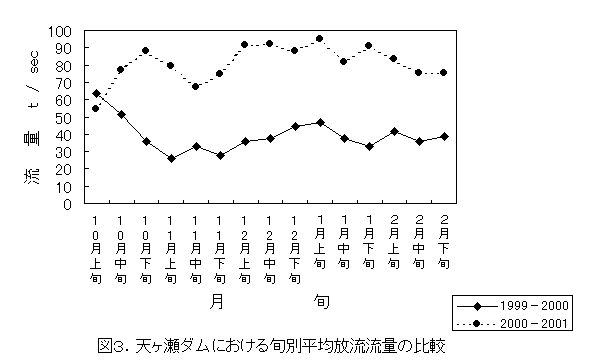 |
Copyright (C) Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.